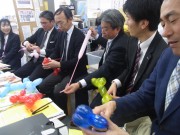05/19
2014

産直市場グリーンファームの現場
年商10億円、年間集客数60万人、
生産者数2500名を誇る直売所が長野県伊那市にある。
その直売所こそ「産直市場グリーンファーム」だ。
先日、そのグリーンファームの
会長にインタビューするにあたって、
現地へと足を運んできた。
というのも、仕事の実情を
しっかりと理解するためには、
現場に直接行くことが必要不可欠なのだ。
そこには、本やデータなどでは
得られない発見があるからだ。
グリーンファームまでは、
伊那市の駅から3キロの道のり。
3キロといっても、実際は急な坂あり、
高台あり、農道ありと大変なものだった。
すると、農道の横に車が多く出入りする小屋や
ビニールハウスばかりが並ぶところが見えてくる。
その中を覗いてみると、「これでも本部です」と
いった看板がかけてある。
なんとそこがまさにグリーンファームの中枢なのだ。
失礼ながら、どう見てもそこまでの
業績を残せるような外観には見えない。
しかし、先日お邪魔したときは(休日であったが…)
直売所の中に数台あるレジには常に4~5人が並んでいた。
では、なぜこんなにも多くの
生活者に愛されているのだろうか。
それは、お客さまと生産者、
そして販売員のみんなが笑顔だということに
理由(わけ)があるのだろう。
私が見た中の驚きは、プラスチックの桶に
ヒキガエルが売られていて、
その日に6匹が買われたという。
えっ?? 誰がどんな目的で??
この雰囲気であり、活気がグリーンファームの
“人気”に繋がるのだろう。
とにかく、ここに集まる“人の気”がいいのだ。
もしかしたら、お客さまはこの“人の気”に
惹かれて来ているのかもしれない。
グリーンファームは20年をかけて、
この“人の気”を試行錯誤して築き上げたという。
結果、この“人気”に吸い寄せられた
お客さまが絶えず買い物に来続けて、
あの業績に繋がっているのだろうと納得する。
いわばこの“人気づくり”こそ、
グリーンファームの仕事道なのだ。
おそらく、この雰囲気は本を読んでも、
インタビューを聞いても理解する
ことはできなかっただろう。
この雰囲気は、職人の業のように言葉では表現できない
“暗黙知”と言うべきもの。“現場を体験することでしか、
理解することはできないということ”。
グリーンファームの仕事道を理解するためには、
本やデータを見るだけではダメということ。
電車を乗り継いでグリーンファーム行ったり、
そこに行くまでに感じることであったり、
現場で空気を感じないとダメだということだ。
まさに“現場にこそ仕事道がある!”ということだ。