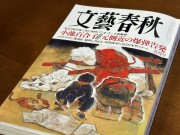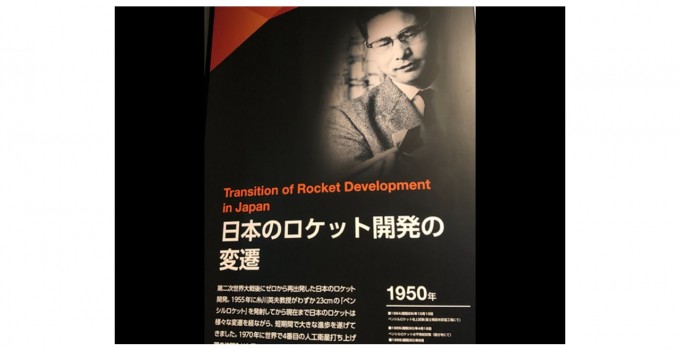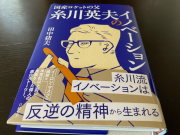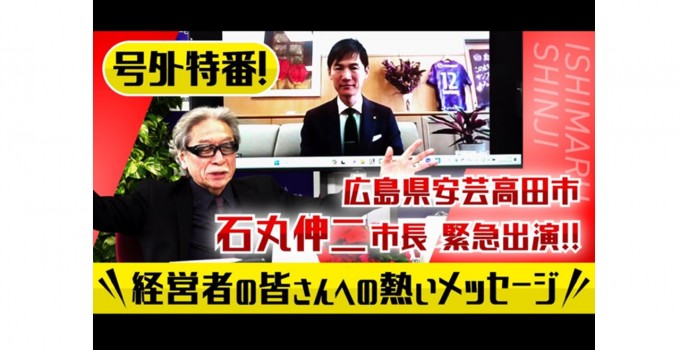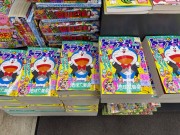04/15
2024
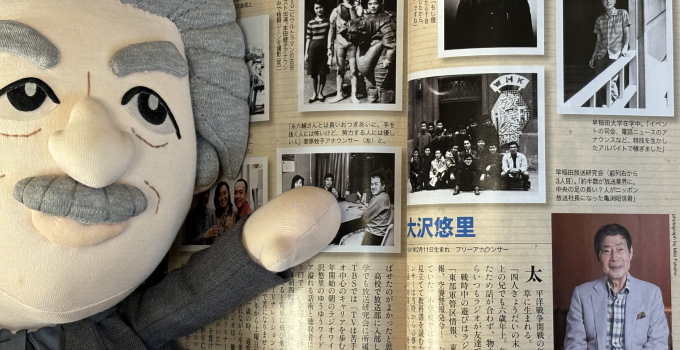
番組が36年も続くには、ワケがある! 大沢悠里さん、文藝春秋5月号に登場。
“Guess who I am.私は誰でしょう?!”
文藝春秋5月号「小さな大物」というコーナーに登場した
あのTBSラジオの大沢悠里さん。
何とラジオ一筋59年。
まさに“レジェンド”と呼ばれるに相応しい
アナウンサーとして紹介されていた。
文藝春秋におけるこのコーナーは、
その人の活躍を写真アルバムを通して紹介する展開。
大沢悠里さんが千歳飴を持つ時代の写真から、早稲田大学在学中、
そしてTBS入社試験用の写真も紹介されていた。
(この入社試験用の写真が、本物より男前なんだなぁ〜)
→永六輔さんとのラジオ番組写真。
「永六輔さんは、手を抜く人には怖いけど努力する人には優しい」
というコメントも。
→パーソナリティでもあった内海桂子・好江師匠との写真。
写真キャプションには“両師匠には人生を教わった”と書かれていた。
→“ゆうゆうワイド”最終回での歴代パートナーたちとの集合写真。
月曜から金曜まで、5人のパートナーと番組展開していたわけで
最終回にはみんなが集まってくれたという。
→そして何といっても毒蝮三太夫さんとの付き合いは60年!
ラジオ番組卒業後、毒蝮さんとゴールデンコンビとして、
『GG放談』つまりジジィ放談としてSpotify独占配信の
Podcast番組として展開している。
【36年も大沢悠里さんの番組が続く理由!】
1986年開始の「大沢悠里のゆうゆうワイド」は36年間続いた長寿番組。
とにかくず〜っと人気番組だったということ。
先程の番組パートナーへの対応もそうだが、
とにかくいつもの関係者を大切にしていた大沢悠里さん。
先日最終回を迎えた人気金曜ドラマ『不適切にもほどがある』にも
1986年、新たに始まったラジオ番組として、ドラマの中で
“ゆうゆうワイド”が紹介され、大沢さんが声の出演をしていた。
確かに昭和の時代から平成、令和と続いた
身近でポピュラー番組だったということ。
◆私の2冊目の著書『儲けないがいい』が出版された時、
大沢さんに番組内で紹介してもらった記憶が…
あ〜大沢悠里さんに書籍の帯の推薦文も書いてもらっていた。
(私もいろいろお世話になっています)
【“番組に関わる人を大事にしたい!”が大沢さんの思い!】
私も何度もTBSにお邪魔して、ゲストを紹介させてもらったり
イベントの打ち合わせをさせてもらっていた。
その度に感じていたのは、ゲストのお客さまはもちろん、
番組のパートナーであり、関係スタッフを大切にしているということ。
大沢さん曰く
「僕がいつもスタッフを可愛がることは、聴いてくれる人たちを
可愛がることだと思ってやってきました。
スタッフを優先して大事にすると、みんな一所懸命に仕事をしてくれるし、
それは聴いている人にも伝わりますから」
ということもあり、大沢さんは毎日の番組の最後に必ず、
出演者とスタッフ全員の名前を読み上げている。
(まるで映画の最後の字幕のように…)
限られた放送時間のなかでもそれを続けたのは、
やっぱりスタッフを大事にしたいという思いから。
まさに大沢悠里流、大人気アナウンサーの仕事道!