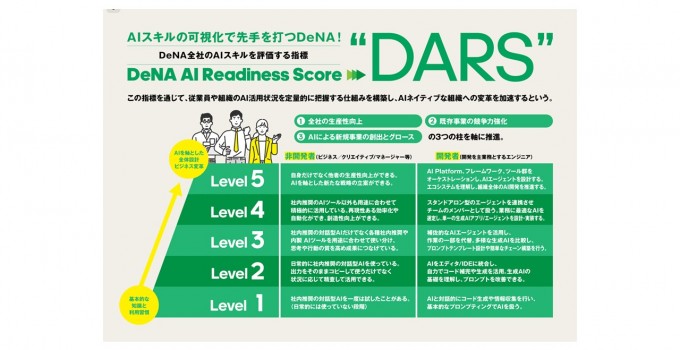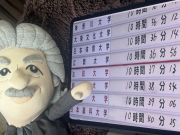12/22
2025

観光大国・日本。ついに世界トップ10入り!
日経MJ恒例の“2025年ヒット商品番付”。
東の横綱は「大阪・関西万博」、
西の横綱は「国宝」。
まぁ、だいたい理解できる。
そんな今年のヒット商品番付を紹介したいわけではなく、
今回注目したいのは、前頭筆頭に紹介されていた
“インバウンド4000万人超”!
円安も働き、オーバーツーリズム問題もあったが、
“観光大国化”は、今後の日本の可能性を語るには重要な要素。
ということで、世界の観光地図が、
今、大きく塗り替えられようとしている。
長年、外国人旅行客数ランキングのトップを走ってきた
フランス、スペイン、アメリカ。
その“指定席”であった上位グループに、
日本が食い込む構図が鮮明になってきた。
◆2024年の外国人旅行客が最も多く訪れた国と地域
1位 フランス 10,000万人(1億人)
2位 スペイン 9,400万人
3位 アメリカ 7,240万人
4位 イタリア 6,850万人
5位 トルコ 5,260万人
6位 メキシコ 4,500万人
7位 香港 4,450万人
8位 イギリス 4,120万人
9位 ギリシャ 4,070万人
かつて政府が掲げた野心的な目標“4000万人越え”が
現実になりつつあるわけだ。
トルコやメキシコ、香港、イギリスといった観光大国と
肩を並べるポジションにきたことは、
日本の観光産業における歴史的な転換点なのかもしれない。
【物価の “安さ”を超えた、日本独自の求心力】
今の日本が世界から選ばれる最大の理由は、
“圧倒的なコストパフォーマンス”と“コンテンツの多様性”、
そして世界に類を見ない日本文化との融合にある。
世界的にインフレが進む中、日本ほど高品質な食、
清潔な宿泊施設、正確な交通インフラを
リーズナブルに享受できる国はない。
さらに、日本の“コンテンツ力”は、世界でも群を抜いている。
京都や奈良に代表される歴史的文化遺産と、
秋葉原や渋谷が発信するアニメ・ポップカルチャー。
静寂と喧噪、伝統と革新が同居する日本は、
あらゆる世代、あらゆる趣味嗜好を持つ
旅行者のニーズを満たす“観光のデパート”なのだろう。
【“数”から“質”へ、そして“地方”へ】
では、日本のインバウンドは今後どこまで伸びるのか。
フランスを目指してのトップ3入りも夢ではないのか。
(年間8000万人〜1億人規模)
そのカギを握るのが“地方への分散”と“高付加価値化”。
東京・大阪・京都は旅人で溢れ既に飽和状態にあり、
オーバーツーリズムの弊害も顕在化している。
しかし、日本の地方にはまだ手つかずの
巨大なポテンシャルが眠っているのだ。
北海道のパウダースノーや沖縄の海だけでなく、
東北の雪景色や山陰の古い町並みなど、
日本人にとっては当たり前の風景が、
外国人には“特別な原風景”として映っているようだ。
今後の日本の勝ち筋は、こうした地方の隠れた魅力を、
富裕層向けのラグジュアリーな体験として磨き上げることにある。
先日観ていたテレビ番組では…
北海道3泊4日→帯広・知床・札幌を巡る約600kmの旅。
プライベートジェットで移動していたわけだが、
その価格、1人280万円だったと記憶している。
一極集中を避け、日本全体を面として観光地化できれば、
“6000万人”という次のステージは
決して高いハードルではないのかもしれない。
日本に来て日本を知ってもらうことは、
必ずや、さまざまなビジネスに好影響を与えてくれるはず!