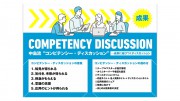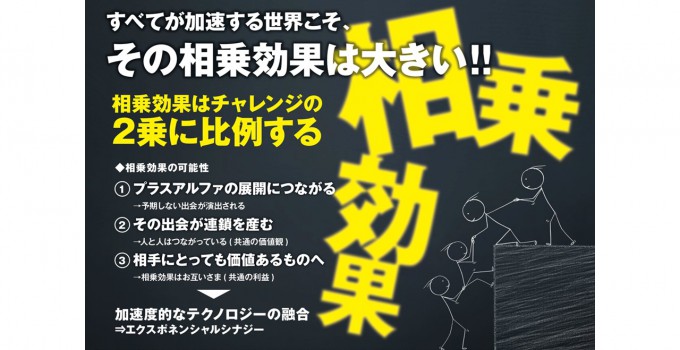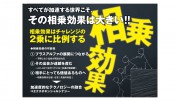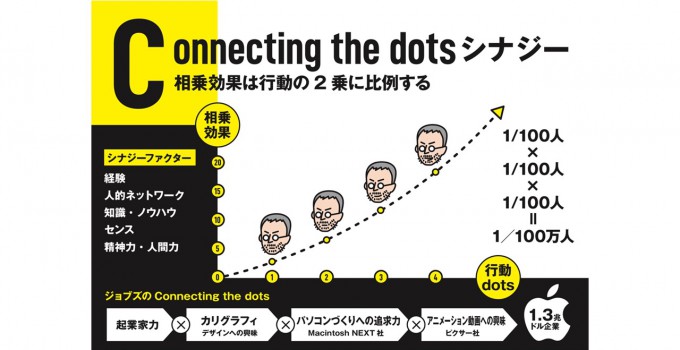06/13
2022
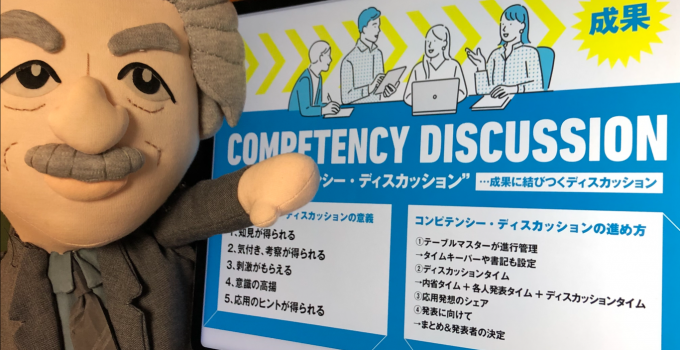
中島流“コンピテンシー・ディスカッション”のシナジー
先にも紹介した“コンピテンシー・ディスカッション”を
覚えているだろうか?
“成果に結びつくディスカッション”の提案ということで
ネーミングしたわけだが、
そのディスカッションの進め方を含めて
かなり細かくルールを作って中島流に仕立て上げたものだ。
“コンピテンシー・ディスカッション”という
名前を付けたのは半年前だが
元々、私は講演会や毎年開催しているリーダーズセミナー等、
あらゆる場でこのコンピテンシーディスカッションを展開している。
通常行われるセミナーやティーチングでは、
知見にまでもっていくには手間がかかるが
同じ体験をした者同士で、しっかりシェアしてディスカッションすると
自分の知見や気づきにつながり易く
自分の日々に活かせるものとなるのだ。
どんなに私が大声で話しても
みなさんに届くわけではないということ。
時間を共有した人たち同士でどこが良かったか、
どんな気づきがあったかをシェアすることで、
より確かな気づきと確かな知見に繋がっていく。
さて、中島流コンピテンシーディスカッションが
いかに相乗効果を起こすかというところに注目したい。
例えば、私がセミナーの中で
1つのテーマに対して5つのポイントを話したとする。
参加者→Aさん、Bさん、Cさん
Aさんは5つのポイントのうち、1~3のポイントはしっかり理解。
Bさんは1、3、5は理解。
Cさんは3~5は理解。
上記のように、ポイントが5つあったとしても
それぞれのポイントの受け止め方や、
自分の気づきにつながるものは3/5くらいだと仮に設定する。
この場合、それで終了するとそのまま止まり。
ところが、ポイントの違うAさん、Bさん、Cさんがシェアし合うと
思考を“シャッフル”することになる。
いかにこのシナジーを活かすかが、
ビジネスにおいては大きな差になってくるのだ。
例えば、毎年開催しているリーダーズセミナーは、
毎月トイレ掃除体験や座禅を組んだり、企業体験等を行うが、
業種業態の違いやビジネス経験の違い、
興味の違い、立場の違い等から捉え方が違ってくる。
それを皆でディスカッションすることによって、
偏りをなくし、
より使いやすい知見、使える情報へと持っていくのだ。
これが多くの人たちが参加しているからこその “シナジー”ということ。
もちろんこのシナジーを活かすことで
次なるビジネスの展開も違ってくるし、
成功への確率も高くなる。
最終的に、シェアでありディスカッションの場は
より相乗効果のあるビジネス展開には
非常に有効で大切ということだ。