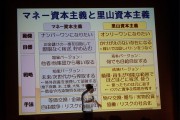10/16
2017

集客力と“衆客力”
集客力とは、
その名の通り「人を集める力」のことである。
では“衆客力”(しゅうかくりょく)とは何か?!
それは、「多くの人が集まった力」を
意味する中島流のキーワードなのである。
というわけで、今回お話したいのは
「衆客力を利用しないでどうする?!」ということなのだ!
先日、代々木公園で開催された北海道フェアに行って来た。
私は、北海道十勝の芽室町の出身なので、
休日に自宅から思わず自転車で会場へ向かった。
代々木公園での開催はもう6年目だという。
フェアの出店者は、企業や飲食店だけでなく、
各自治体もPRの一環としてブースを出しているのだ。
会場に着くと、そこは人、人、人の山!
“北海道フェア”というのは、それだけで物凄い集客力があるものだ。
飲食ブースはどこも行列で、隣の邪魔になるからと、
ブースの裏に回って列をなしているほどだった。
北海道の定番、ウニいくら丼をはじめ、
松尾のジンギスカン、
メロンを豪快に二等分し生クリームをトッピングしたスイーツなど、
多くの人がその味を求めて並んでいた。
さて、これだけの集客力をもつ北海道フェアだが、
このうちのどれだけの人たちが、
北海道の地まで足を運んでくれるだろう。
もちろんこう考えてしまうのは、
今Memuroワインヴァレー構想を展開しているからではあるが…
そう、北海道の地を実際に体験してもらうことが、
より“北海道”のブランディングにつながるということ。
東京でフェアを開けば、これだけ多くのお客さまが
北海道の食に興味を持って集まってくれる。
だが、このフェアをきっかけに、
北海道まで遊びに行きたくなるような仕掛けや工夫はあるのだろうか?
要するに、
中島流“タテの発想”で物事を捉えていくといくことが、
次なるステージに上がるための必須の思考なのだ。
今ここにたくさんのお客さまを集めるだけで満足してはダメということ。
どうにか、十勝に多くの人たちが来てくれたとする。
でも、彼らが東京に戻ったあと、
「次なるお客さま」を巻き込むような行動をしてくれるだろうか?
ただ来てもらって終わりではなく、
その場所の魅力や体験を、どうすれば周囲へ発信してもらえるのか。
そして、リピーターになってもらえるのかなのだ。
これが“衆客力”を活かすということ。
この“衆客力”を活かさずして多くの人が
継続的に来てくれる魅力的な地にはなり得ないのだ。
「今だけ」を見た単純な集客ではなく、
その先の発展や継続を見据え、サービスを作る。
これこそ、中島流“衆客力”の可能性であり、
選ばれるサービスを作る上で欠かせない視点なのである!