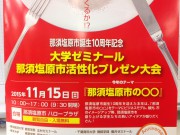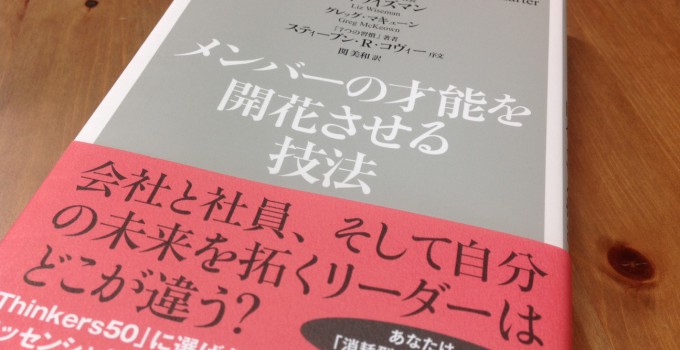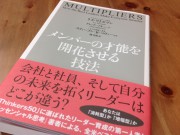12/07
2015

実践が先か、ノウハウが先か
卵が先か、鶏が先か。
なんて言葉があるように、
経営において“実践(実践しながらノウハウを構築するのか)”と
“ノウハウ(一般的な経営ノウハウを持って事に当たるのか)”
のどちらを優先するべきかに悩む人もいるかもしれない。
私自身、クリエイティブの会社を経営して33年経つが、
経営だけでなく経営デザイナーとして
コンサルティング活動を行う中で、
同じようなことを思い浮かべたことがある。
そんな中で私がたどり着いた答えは、
“実践”と“ノウハウ”のどちらかを優先するのではなく、
双方を活用して使い分けることが大切だということだ。
この考えは、現在取り組んでいる
「芽室ワインヴァレー構想」におけるまちづくりでも実感している。
現在、北海道の十勝にある芽室町にて、
ぶどう園とワイナリーを設置し、
そこを拠点としてさまざまな地域活性化に
繋げる活動を行おうとしている。
ここではぶどうやワインをつくるだけでなく、
その地域のまちづくりもお手伝いしようとしているのだが、
そこで得た情報を“里山デザイナー”として
多方面に発信していこうとしているのだ。
ここで得た情報やノウハウは、
他の地域のまちづくりにも活かされる。
まさに、まちづくりの実践と、
“里山デザイナー”としてのノウハウの発信という
双方のキャッチボールがより奥行きのある情報となり、
多方面に効果をもたらしていけると思うのだ。
このように、実践で得た情報をノウハウとして活用し、
更なる実践へとつなげることで、その効果は一部に限らず、
さまざまな方面へ広がっていく。
この相乗効果こそ、中島流の仕事術の真骨頂だといえるのだ。
今回、地域活性につなげるためのまちづくりを
中島流に“里山デザイン”として取り組んでいる
(ワイナリー構想もそのうちのひとつだ)。
いまいくつかの企業が取り組んでいるような、
“里山”を活かしたビジネスは、
これからの日本にますます求められていくだろう。
だからこそ、ビジネスにおける里山の活用を提案する
“里山デザイナー”として、
さまざまな実践とノウハウによる相乗効果を広げていきたい。
卵が先か、鶏が先か。
どちらが先でも後でもなく、新しいチャレンジでは、
常に実践とノウハウの構築のキャッチボールが大切だ。
この相乗効果を生かさずして、
これからの地域の活性化はないのだ。
芽室ワインヴァレー構想に乞うご期待!