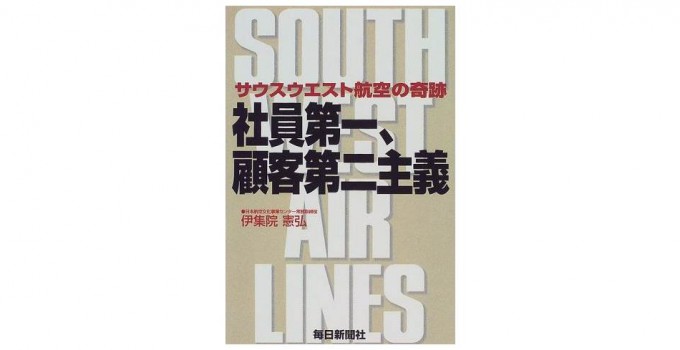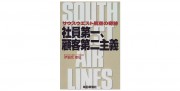05/26
2014

小林史麿会長の善循環シナジー
「直売所は公共事業だ!」
グリーンファームの小林史麿(ふみまろ)会長の言葉である。
公共事業というと、お役所先導で税金を投入する
道路工事やハコモノ作りが思い浮かぶけれど…
一体なぜ、農産物の直売所が公共事業になるのだろう??
その答えはグリーンファームを知れば見えてくる。
長野県伊那市にあるグリーンファームでは、
地元の人たちおよそ60人が働いている。
売られているのは、地元農家が中心となり
生産した新鮮な野菜や特産品だ。
生産者約2,500人の平均年齢はおよそ70歳、
高齢者がほとんどだが皆がイキイキと楽しそうに
生産活動をしている。
さらに、敷地内には動物園もあり、
訪れる人たちにとってはちょっとした
テーマパークのような楽しみもあるのだ。
もちろん、こういった充実した直売所がある!
ということが伊那市のブランディングにも
繋がっていることは言うまでもない。
海外20カ国以上から視察がやってくるというのも納得だ。
・地域雇用の産出
・高齢者の生きがいづくり・健康づくり
・地元農家の活性化
・地域のブランディング などなど…
整理してみれば、
これらは本来なら伊那市が地域活性化の
公共事業としてやってもいいようなことだ。
それを、小林会長は20年かけて、
充実した形で達成してしまったのである。
「直売所は公共事業だ」というのは、そういう意味だろう。
グリーンファームの年間集客数は約60万人。
売り上げは10億円にも及ぶというが、
こうした経営的な成功の裏には、
単なる商売に終わらない善が善を呼ぶ好循環のシナジーがある。
お客様は新鮮な野菜や活気ある市場の様子を見ることで笑顔になり、、
それを見た生産者・従業員にもやる気が満ちてくる
(ここは生産者が購入者でもあり、よく足を運んでいるという)。
そのやる気が魅力ある商品づくりにつながり、
さらなるお客様の満足になる。
小林会長の“仕事道”が、
このすばらしい相乗効果をつくり出したわけだ。
まさに、シナジースペシャルにふさわしい
『善循環シナジー』!
小林会長をお招きして、
じっくりとお話を伺うBUSINESS LAB.は
Inter FMで6月1日・6月8日、日曜朝の6:00から!
グリーンファームのこと、
経営のこと、たっぷり聞いちゃいます!