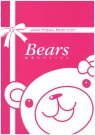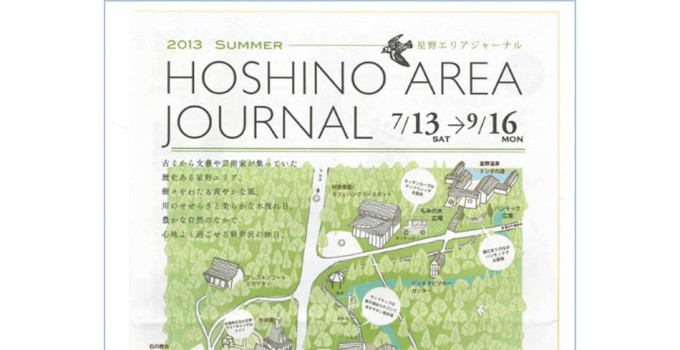09/24
2013

先手必勝ならぬ、先手必照
先手を打つ商品開発は、
思わぬ(思っていたかも)相乗効果を得られる。
家事代行を行う、株式会社ベアーズ。
その創業経営者の高橋ゆき氏はビジ達でも度々ご紹介し、
私がパーソナリティを務める『BUSINESS LAB.』にもご出演いただいた。
先日、NBC(東京ニュービジネス協議会)のイベントで
“広報”という角度から改めてベアーズの事業展開を聴いたのだが、
商品開発の内容とタイミングを理解すると見えてくるものがある。
・2006年法人会員制度導入
女性の社会進出が増え、今や共働きをする夫婦もかなり多い。
それによって家事をこなすことが難しいという女性が増えている。
そんな女性に向けて、家事代行を会社の
新しい形の福利厚生として取り入れてもらうという提案。
・2010年ファミリーサポートサービス
介護は介護を行う家族にも非常に負担の大きいもの。
このファミリーサポートサービスは、
そんな介護する側の人をサポートするサービスだ。
・2012年シニアサポートR60
これは介護サポートサービスではなく、
定年を迎えセカンドライフを送る
アクティブシニアに向けたサービスだ。
この取り上げた3つの商品に共通していることは、
社会背景や時代背景にマッチし、
さらにターゲットが絞られた商品開発がされているということ。
しかも、市場として人々が注目する前に先手を打って
商品開発を行っているのだ。
先手を打てば業界のリーダーシップをとれるだけでなく、
メディアが注目してくれる。
時代の変化を伝えるメディアは、その変化を取り込んだ社会現象、
すなわち新しいサービスや商品に着目して紹介するということだ。
実はベアーズは1999年の創業以来、
ほとんど広告費をかけていないという。
しかし、先手を打って商品開発をしているため、
広報の役割を多くのメディアが担ってくれているのだ。
先手必勝といえるが、
先手はメディアが“必照”してくれるのだ。
ターゲットを絞り込んだ商品開発が、
需要をつくると共に、メディアの注目も集めるということ。