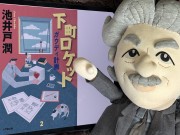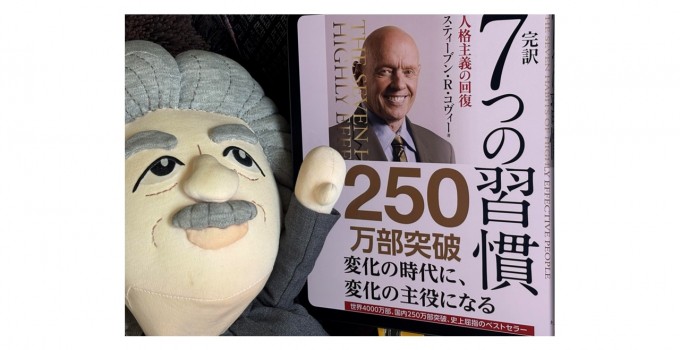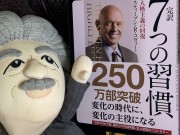09/29
2025

井上陽水が自分に捧ぐ“新・人生がニ度あれば”
井上陽水氏のアルバムを久々にSpotifyで聴いていて
思わず口ずさみ、その意味を改めて考えてみた。
タイトルは『人生が2度あれば』。
↓ ↓
父は今年二月で六十五
顔のシワはふえてゆくばかり
仕事に追われ
このごろやっとゆとりができた
父の湯呑み茶碗は欠けている
それにお茶を入れて飲んでいる
湯飲みに写る
自分の顔をじっと見ている
人生が二度あれば
この人生が二度あれば
母は今年九月で六十四
子供だけの為に年とった
母の細い手
つけもの石を持ち上げている
そんな母を見てると人生が誰の為にあるのかわからない
子供を育て
家族の為に年老いた母
人生が二度あれば
この人生が二度あれば
【この曲がデビュー曲だったという?!】
父は今年で65…
母は今年で64…
この歌がデビュー曲(再デビュー)としてリリースされた
1972年は、井上陽水氏は24歳。
福岡県飯塚市で育った。
(私はまだ17歳で北海道にいた)
へ〜よく24歳でこの歌詞に至ったものだ。
当時から、それまでの人たちと何かが違うと思ってはいたが…
やっぱり才能とセンスだろうか?!
そして1973年にリリースしたアルバム「氷の世界」は
日本初のミリオンセラー作品に!
「窓の外ではリンゴ売り
声をからしてリンゴ売り
きっと誰かがふざけて
リンゴ売りのまねをしているだけなんだろう」
(これは「氷の世界」の歌詞だが…なぜこんな歌詞に?!)
その後「傘がない」「夢の中へ」「いっそセレナーデ」
「リバーサイド ホテル」「少年時代」などの名曲を多数発表した。
この私でさえ、どの曲も大体は口ずさむことができる。
【「新・人生が二度あれば」を歌って欲しい!】
シンガーソングライターとしてデビューして52年。
井上氏はさまざまなヒット曲を世の中に発信してきた。
私は中森明菜さんが歌っていた
「飾りじゃないのよ涙は」を思い出す。
(流石にあの高いキーでは、歌えなかった記憶が…)
中森さんにとっては、アイドルからアーティストへの
転機となった重要な曲だ。
井上陽水氏は団塊の世代であり、もう77歳だという。
当時の“人生が二度あれば”の両親よりすでに年老いている。
そこで提案だが、今度は父や母ではなく
自分をテーマに「人生が二度あれば」を歌って欲しい。
どんな違う自分を想像するのか?!
果たしてどんな歌詞になるのだろう。
もちろん、曲は一緒で歌って欲しいのだが…
さて、私なら…人生が二度あれば…