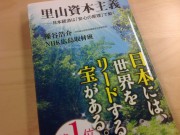11/25
2014

“里山ビジネス”の原点
大ヒット中の書籍『里山資本主義』。
この本を読んでいると、
内容がやけに身近に感じられた。
なぜなら、そこで推奨されている各地での活動は、
私が“里山主義”と提唱している少し前の、北海道十勝での
生活(ビジネス)と多くの点で共通しているからだ。
十勝の中でも、芽室町上美生という
家が数百件程度しかない地域がある。
私はその、ほとんどの家が農家の町で
生活を送っていた。
そこに住む農家の人たちは忙しく、
衣類などを買うためには、
片道16km以上の道のりを越えて、
市街地まで行かなくてはならなかった。
また、その頃は(1955~1970年)、
車やバイクもなかった。
そのため、気軽に衣類などを
買いに行くことが難しかった。
その中で、衣類などの生活雑貨を買い付け、
地域の人たちにお届けしていたのが、
私の母だったのだ。
母は、夏場は自転車で、冬は歩いて、
地域の人たちのニーズに
合わせた生活雑貨を届けた。
このように、里山地域ならではの役割の実践も、
中島流で言うところの“里山ビジネス”なのだ。
そして、上美生地域の人は、他にも自分の生業を活かし、
互いに不足している部分を補う商売を行っていた。
例えば、農家の人が、畑で取れた大豆を1升分持っていくと、
何丁かの豆腐に換えてくれる豆腐屋さん。
牛を飼っていない農家の人が、
100円を持って酪農農家に行くと、
一升ビンいっぱいの牛乳を入れてくれるのだ。
つまり、その地域にないものは、
地域の数少ないお店や誰かが用意するのだが、
それ以外は地域内での物々交換で賄われていた。
すなわち、不必要なお金が動かない、
無駄を省いた流通システムで北海道の里山地域は、
循環していたのだ。
足りない物を補足し合い、
個々の家の生業を活かした流通で相乗効果を生み、
小さい規模ながらも地域社会を成立させていた
上美生地域のビジネスは、里山ビジネスの原点と言ってよいだろう。