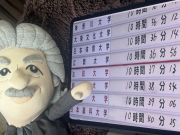10/27
2025

ワインによる地域再生へ! 持続可能な“余市町”への挑戦!
ある新聞に「“ワインで一点突破”余市町」という記事が…
ご存知の方も多いと思うが、北海道余市町は
NHK連続テレビ小説「マッサン」(2014年)で注目された
ニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝の地元である。
この時も余市町は結構注目されていたのだが、
もっともっと仕掛け、交流人口を多くしなくては、
20年後には“消滅可能性自治体”となってしまうという。
実は日本の地方自治体が直面する課題は
少子高齢化や人口減少だけではない。
それらに伴う経済衰退をどう食い止めるかが問われている。
そこで余市町が掲げる“ワインで一点突破”戦略は、
その解決策の一つとして注目を集めている。
この戦略により、余市は品種転換と補助金制度を駆使し、
ワイン産業の基盤強化を実現しようとしているのだ。
→この“ビジ達”読者はご存知と思うが…
私は2015年に北海道十勝の芽室町(東北海道)で
ワインを地域の“6次化商品”と位置付け、
同様のコンセプトで“memuroワインヴァレー構想”を
立ち上げ、ブランディングであり
交流人口の増強を図ろうと展開したのだが…
(残念ながらトラブルとコロナ禍が襲ってきて、
プロジェクトは頓挫してしまった!?)
【ワインぶどうの品種転換と補助金制度の活用へ!】
余市町は、ドイツ系品種から
フランス系品種への転換を進めてきた。
国際的な需要が高いピノノワールやシャルドネを
選択することで、町の認知度向上と
観光誘致を図ろうとしている。
最大150万円の補助金は生産者の負担を軽減し、
結果として栽培面積の拡大に寄与した。
この5年間で“ピノノワール種”10ヘクタールの増加は、
町の継続的な取り組みとその効果の現れといえる。
結果として、ワインを基軸とした観光・地域活性化も進んでいる。
2024年度には、ふるさと納税寄付額が15億円を突破し、
ワインを中心にした地域産品が注目されている。
観光客の増加により、町内での宿泊施設の増加や
長期滞在型観光の拡大にも繋がっている。
(素晴らしい!私と同様の目論みで上手く推進している!)
【持続可能な町の発展に向けて!】
余市町の例に見るように、
地方自治体が持続可能な発展をするためには、
地域の特色を生かしたブランディングが不可欠。
一方、国際連携を通じた気候変動対応や、
収益機会の確保も重要。
この町が続ける挑戦は他の地域にとっても
参考となるモデルケースであることは間違いないだろう。
地方自治体は戦略的な展開を通して
生き残りを目指さなければならない。
地域のブランディングを通じたこういった発展モデルは、
40%が消滅の危機とされる全国の自治体にとって、
一筋の光となるだろう。
これからは全国約1700のさまざまな自治体が、
“消滅可能性自治体”とならないがために
あらゆる活性化のためのアプローチを
していくことになるのだろう。
私ももう少し若ければ、新たなビジネスドメインとして
全国の地方自治体の活性化に向けて
アプローチしていくのだが…
残念ながら、度々飛行機に乗ることも億劫になってきているのだ。