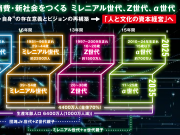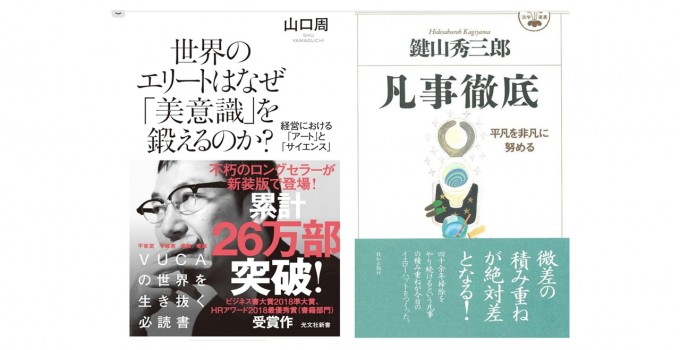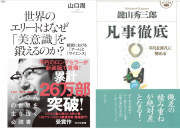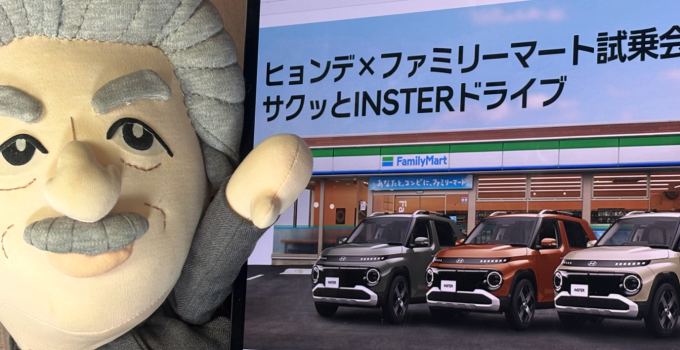02/03
2026
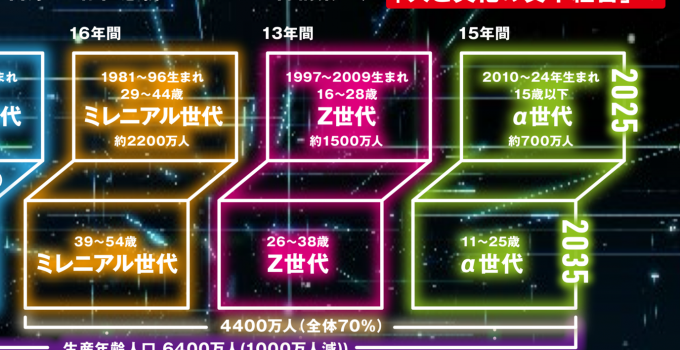
“就社”から“就志”へ! Z世代・α世代の選び方。
(メイン画像から抜粋したZ世代・α世代に注目してほしい)
生成AI“Gemini”との対話から飛び出した、
これからの時代を生き抜くキーワード。
「週3正社員」という働き方の変革も刺激的だが、
もう一つ、採用の本質を突く言葉があった。
「Z世代・α世代が選ぶのは“就職”ではなく
“就社”でもなく“就志”である」という視点。
これは単なる言葉遊びではない。
昭和、平成、そして令和へと続く人材獲得競争の
パラダイムシフトを、この一語が見事に言い当てている。
2030年、2040年を見据えた経営において、
この“就志”という感覚を理解できるかどうかが、
企業の命運を分けることになるのかもしれない。
「就社→会社に入る」から
「就志→志を持って仕事を選ぶ」へのシフト。
会社名や知名度、安定性よりも、
「何をしたいか」「自分らしく働けるか」という
個人の価値観や目的(志)を重視する傾向が強まっている。
【規模や安定性よりも“何のために”働くのか?!】
かつて昭和や平成の初期、
多くの人々が求めたのは“就社”。
会社の規模、知名度、安定性。
寄らば大樹の陰とばかりに、組織という“器”に
所属すること自体がステータスであり、安心の源泉だった。
しかし、生まれた時からインターネットがあり、
情報に溢れ、同時に環境問題や格差といった社会課題を
身近に感じてきたZ世代やα世代(デジタルネイティブ)は違う。
彼らにとって、単に大きな箱に入ることは重要ではない。
彼らが真に求めているのは、その会社が社会において
どのような存在意義を持ち、
何のために事業を行っているのかという
“志(パーパス)”への共感だ。
“この会社で働くことが、自分の人生や社会にとって
どんな意味を持つのか”ということ。
【採用サイトよりも“経営者の言葉”を磨け】
多くの企業が、若手を採用しようと躍起になり、
見栄えの良い採用サイトやSNSの発信に力を入れている。
がしかし、彼らが求めているのは、飾られたキャッチコピーや
洗練されたデザインではない。
経営者自身の口から語られる、嘘偽りのない“言葉”だ。
このビジ達でも度々テーマとしてきた“Why”。
なぜこの事業をやるのか、この会社はどこへ向かうのか。
その熱量と本気度(=志)に入り口で合致して初めて、
彼らはその企業に関心を持つ。
だがここで重要なのは、“志”への共感が
すべてではないということ。
“志”はあくまで“入り口”であり、必須の参加資格である。
このゲートを通過して初めて、
“では、具体的な仕事内容はどうなのか?”
“給料は適正か?”という次の議論へと向かう。
【中小企業にとって“就志”の時代は、追い風かも?!】
では、次なる実質的内容とは…?!
【1】スキルアップや成長の機会が多く 市場価値を高められるか
【2】給与・待遇が良いか
【3】職場の雰囲気・社風・コミュニケーションが良いか
【4】魅力的なサービス・プロダクトであるか
【5】将来性のある市場・事業であるか
【6】SDGs(社会貢献や持続可能性)への取り組みがあるか
かつては給料や待遇が入り口だったかもしれないが、
今は順序が逆転している。
“志”なき好待遇は、彼らにとって怪しい餌でしかない。
逆に言えば、高い志で結ばれた関係性の上であれば、
仕事の厳しさも、待遇の多寡についての議論も、
建設的な“パートナーシップ”として成立する。
“就志”の時代は、中小・中堅企業にとって、
これは追い風なのかも知れない。
規模で勝てなくとも、志の高さと純粋さであれば、
大企業を凌駕できるからだ。