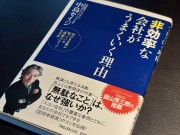01/19
2026

2026年スポーツの新たな幕開け。 筋書きのないドラマとエンタメの未来。
あなたは2026年、どのスポーツに注目?
ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート、カーリング、
スキージャンプ、スノボ…
それとも大谷翔平も登場するWBCの連覇?!
いや〜今回48チームも登場し、
優勝を目指して戦うというサッカーW杯?!
経営者会議の懇親会の後も、スポーツニュースを意識して
家に直帰する私なわけだが…
今年は確かにスポーツイベントが目白押しで、楽しみは多い!
まずは北海道十勝の出身者として、スピードスケートの
高木美帆選手の1500メートルに期待したい。
金2個を含む計7個のメダルを手にした彼女だが…
「この4年間必要なことをがむしゃらに求め続けてきた。
チームをつくった動機もすべて、五輪でメダルを取りたい、
1500Mで勝ちたいから」という。
このストーリーとそこで展開される筋書きのないドラマが
私たちをワクワクさせるのだ。
【エンタメ産業は、この筋書きのないドラマとどう戦う?!】
Jリーグ、Bリーグ、Vリーグ、Xリーグ、Tリーグ…
実は、AリーグからZリーグまで、アルファベット26文字
すべて使われているという。
今や、さまざまなスポーツ界が、
エンタメの演出を次々と取り入れ、盛り上げを図っている。
アメリカのコンサートや映画ショーの演出や技術と結びつき、
これまでにない体験を生み出すことに期待が高まっているのだ。
まさに、スポーツイベントの大量開催による
“ライブ体験の加速”である。
ある新聞のコラムに書かれていたことだが…
「これは筋書きのない時間のダッシュ。
日本人選手であり、“推し”の活躍といったスポーツの熱狂に
人々が没入すればするほど、映画や演劇といった
既存のフィクションが地味に見えてしまう。
エンタメ産業は今、かつてない最強のライバルと向き合っている」
うんうん、分かる気がする。
だから、テレビ番組のエンタメと言いながらも
クイズ番組、歌謡番組、スポーツ系番組でも
“サスケ”のように筋書きのない競争番組が多くなっているのだ。
【フィクションにしかできない没入感の演出?!】
では、既存の“エンタメ”はどう生き残るべきか。
答えの一つは、“テクノロジーとの協奏関係”にあるだろう。
例えば、ディズニーとOpenAIの提携が象徴するように、
生成AIはもはや敵ではない。
誰もがクリエイターになれる時代、プロに求められるのは
“圧倒的な世界観の構築”となる。
AIが作る短尺動画や、スポーツの瞬発的な興奮とは異なる、
長時間浸りたくなるような濃密な物語体験。
もしかしたら“ジブリの世界”などはその例かもしれない。
そのジブリ的創造性に、最新技術力をも活かし
視聴者を現実から完全に切り離すような没入感を
演出できるかである。
【“推し”の熱量を物語へ還流せよ】
さらに、スポーツの熱狂から学ぶべきは“推し”の力。
単に作品を提供するのではなく、
制作過程や裏側のストーリーを公開し、
ファンを“制作の仲間”として巻き込む戦略が重要となる。
スポーツ選手への応援と同じ熱量を、架空のキャラクターや
演者に注ぎ込めるような仕掛けづくりをする。
『国宝』にみる上映時間3時間という意味ある長編の物語と、
W主演の“吉沢亮”であり“横浜流星”だろうか?!
兵庫県豊岡市の“出石永楽館”であり、滋賀県“びわ湖大津館”には、
聖地巡礼スポットとして多くの人たちが訪れているという。
まぁとにかく、“エンタメ”は既存の枠を超え、
スポーツとのコラボレーションや
テクノロジーの活用を通じて進化する必要があるということだ。