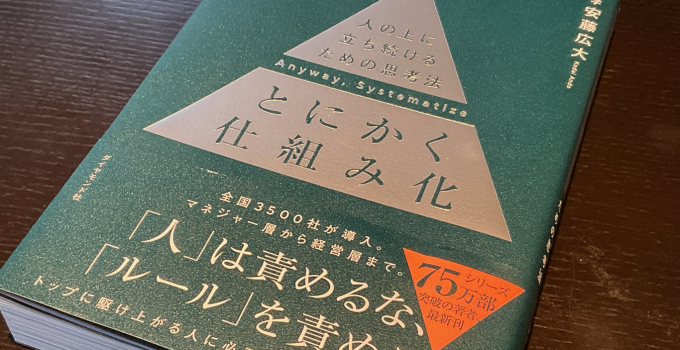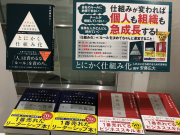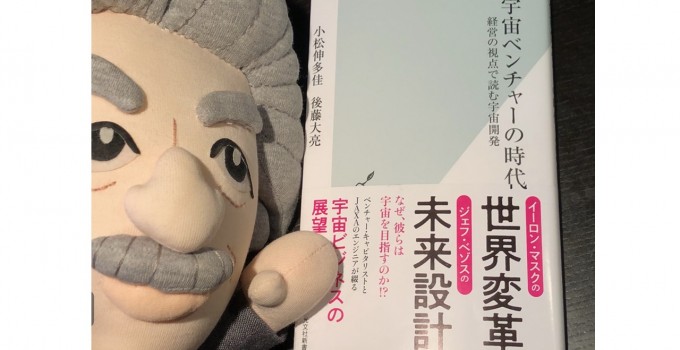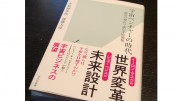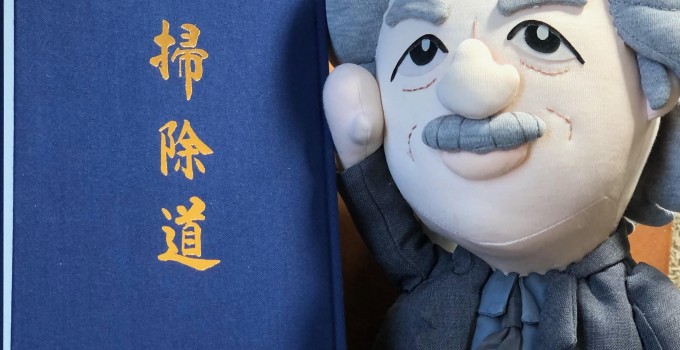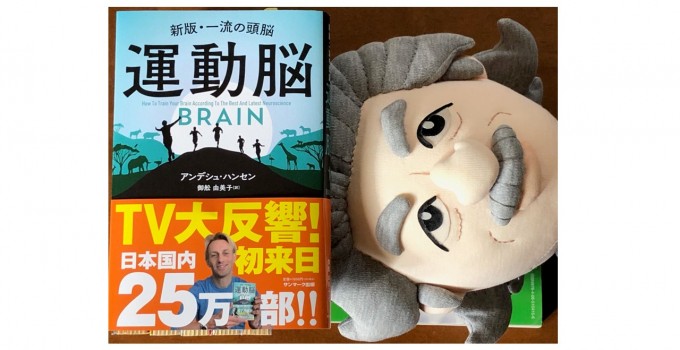08/21
2023
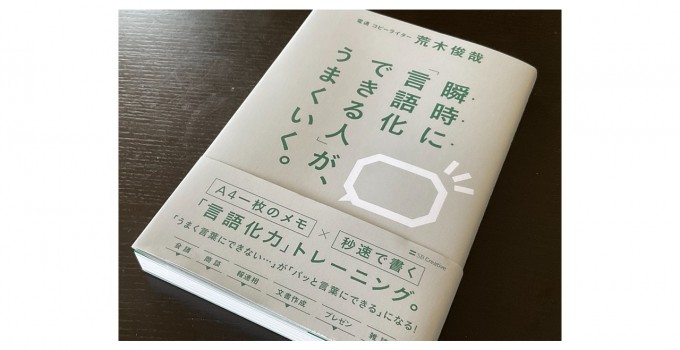
『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』 荒木俊哉著
このところ丸善本店で、“言語化できる人”という表現が気になり
つい手に取ってみたのがこの本。
著者は電通コピーライターの荒木俊哉(しゅんや)氏。
“ふむふむ”というところがあちこちにあったのだ。
ご存知の100万部を超えたという『伝え方が9割』という書籍もあるが、
この荒木氏は“伝え方”より“言語化力”こそが大事だという。
(結構『伝え方が9割』を意識して書いている風があちこちに
表現されているところが面白い)
本来「何を言うか」という“言う内容”そのものが人の心を打つのであって、
内容の薄い話にいくら「どう言うか」の工夫を施しても、
人はそれが表面的であることを敏感に見破ってしまう。
そして仕事における評価は、どう言うかより何を言うかで決まる。
“伝え方”とは、自分の言いたいことを言語化した後の行程のスキルであり、
コミュニケーションの本質は“伝え方”より“言語化力”だと。
(うんうん、分かるような気もする)
【“言語化力”を身につけるためのトレーニング方法?】
この書籍では、”伝え方”より“言語化力”だというだけでなく、
どうしたら“言語化力”を磨けるのかを
著者がコピーライターだったころの試行錯誤から
あるトレーニングに行き着いたことを語ってくれている。
言語化力を身につける上で大事な行為は、
自分が考えたことを“とりあえず書き出してみる”という行為。
私たちが物事に対して抱いている“思いや意見”は
そのほとんどが言葉にならない漠然としたイメージとして
脳の中に蓄積されているだけ。
言葉になっているのはほんの一部。
残りは言葉にならない状態で無意識下に。
そこで…
【その1】 これら言葉にならない状態のものを“とりあえず書き出してみる”
【その2】 すると自分の思いや意見を客観的に眺められることに
【その3】 書き出された言葉がトリガーになり思いが言語化に
【その4】 そこに追加で言語化された思いや意見が再度トリガーとなり再認識
(これらの表現は私的にまとめてしまったが…)
これら思いや意見が大量にストックされることで、
急に意見を求められても、サッと言葉で返すことができようになるという。
これが“言語化力のある状態”だと。
この本ではその後シンプルなトレーニング“実践編”とか“発展編”が
紹介されているわけだが…
(興味のある方は購入して研究していただきたい)
さて、いかがだろうか?
“もの書き”に近い仕事をしてる人は納得するのでは?!
さて、私はこの20年“ビジネスの達人”をサボらずしっかり配信してきた。
そのお陰で、セミナーや講演会でもコンテンツに困らないし、
なぜか喋りもアドリブも効き、スムーズになったような気がするのだ。
“アラ古稀”だというのに、年齢による劣化も少なく
その昔よりビジ達の発信内容もセミナー等での喋りも…
(これはみなさんが評価することですが…)
ということで、今でも週に2本は中島流の“思いや意見”を文章にしていることで
無意識を“意識化”にし、それをさらに中島流の“考えであり発想”とするために
「言語化力」のトレーニングを毎週繰り返ししているということ。
さて、いくつまで続けられるのだろう。
大先輩の五木寛之氏がまだあちこちで連載していることを思うと…
(思わず、大御所の五木さんを引き合いに出してしまった)