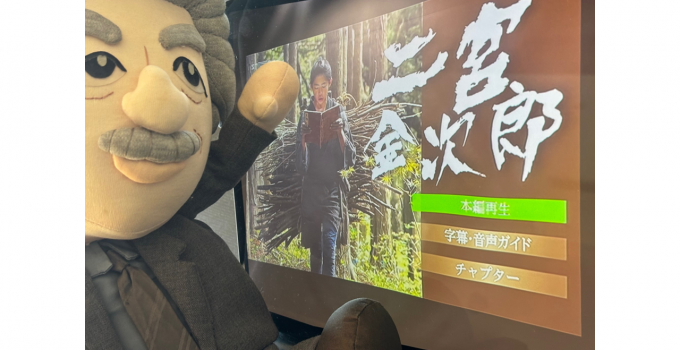03/24
2025

追悼“鍵山秀三郎相談役” ありがとうございました。
鍵山秀三郎相談役、人として経営者として、
いろいろ学ばせていただきありがとございました。
お陰さまで、人としても経営者としても道を外さず、
少しは世の中に貢献できているのではと思っております。
↓ ↓ ↓
「凡事徹底」はじめ、
「大きな努力で小さな成果」、
「平凡なことを非凡に努める」、
「微差、僅差の積み重ねが遂には絶対差となる」
「益はなくとも意味はある」
人が疎かにしてしまいがちな真理に光を当てる
相談役の言葉の数々は、
今なお多くの人に影響を与えつづけているはず。
私が鍵山秀三郎相談役を知ったのは、多分30年ほど前。
お会いしたのは船井総研・創業者の船井幸雄さんが
開催していたコスモスクラブのセミナーだったと記憶。
そしてある情報誌の取材で、イエローハット創業者として
鍵山秀三郎氏を取材することになったのだ。
中目黒の新しい本社を訪ね、応接室に通され
鍵山さんは冒頭で…
「中島さん、“小さな努力で大きな成果”と
“大きな努力で小さな成果”とどちらがいいと思いますか?」
と投げかけてきた。
私は「もちろん“小さな努力で大きな成果”を求めます」
と答えるわけだが…
鍵山さんのその時の嬉しそうな顔が忘れられない。
その後、まさか私が“掃除に学ぶ会・日本を美しくする会”に
所属することになるとは⁈
【DVDの発刊で、“鍵山秀三郎”という人を知ることに!】
2005年ごろ、鍵山秀三郎相談役が実演解説する
“トイレ掃除のやり方と哲学”DVD「掃除の道」を発刊。
創るなら“掃除に学ぶ会”の関係者だけでなく、
誰もが買いたくなるDVDにしましょうと、
私がプロデューサーとなり弊社クオーターバックを発刊元とした。
すなわち我が社がリスクを持っての発刊としたのだ。
それを知った鍵山相談役は、初版の6,000本のうち
半分の3,000本をイエローハットで購入してくれた。
(鍵山相談役に感謝!だった)
お陰さまでDVDは順調に売れ再販することとなり、
次なるDVDの街頭清掃編や掃除人のための道具と使い方、
その手順も解説する“ポケットブック”も出版することに。
そしてその後、“日本を美しくする会”が運営する
「鍵山塾」のプロデューサーとしても
お手伝いさせていただくことに。
お陰さまで鍵山相談役の近くでいろいろな人とも出会い
多くの勉強もさせてもらったのだ。
今、このようなことを書き記していて
改めて、鍵山相談役の近くという恵まれた環境で
お世話になっていたことを確認した次第。
→相談役、本当にありがとうございました。
【私の記憶に残るお話は…】
2019年3月に靖國神社で開催された
掃除に学ぶ会“便教会”での、
10分程度のあくまで挨拶的お話。
↓ ↓ ↓
「日本は戦後、経済的な国力が増加するにつれて
教育の場と機会が豊かになり高学歴の人が多くなりました。
しかし、“智”の面は向上しましたが、それに反比例して
“情”の面が衰退していったのです。
学歴は高くなり“智”の面は著しく向上したのに、
総合力である「人間力」は低下したのです。
「人間力」とは、“智”と“情”の総和ですので、
“情”の面が退化すれば人間力という総和力は低下します。
“情”とは周囲の人に気を配り思いやる心です。
“智”の不足は“情”で補えますが、
“情”の不足は“智”では補うことができないのです。
だから先生方、“智”のための勉強だけでなく
“情”の分かる人たちを育んでくださいね」
→感動!